BLOG
クラウドサービスの導入を成功させるコツ
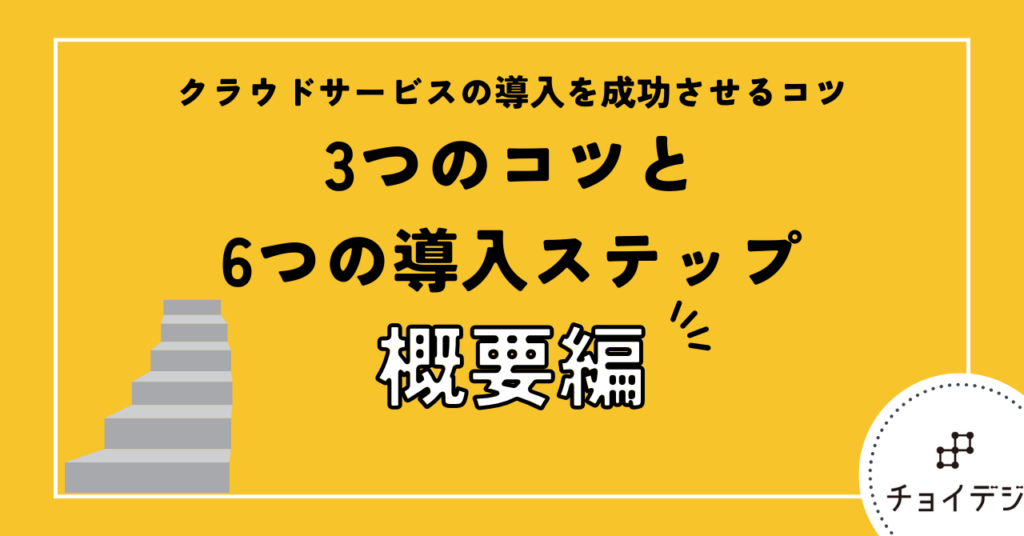
<目次>
クラウドサービスの落とし穴
コロナ化をきっかけに取組が加速したテレワーク、オンライン会議の恒常化、DXの推進などといった背景から、企業のIT基盤全体をクラウドに移行する企業がますます増えています。
しかし、クラウドサービスを導入した企業の中には、クラウドサービスの導入による業務改善を期待していたものの、「あまり効果がなかった」「むしろマイナスの効果があった」などと回答する企業が少なからず存在することも事実です。綿密な計画策定やコストの検討などを行わずに導入を進めてしまうと、大きな失敗につながってしまいます。
着実にクラウドサービスの導入を進め、自社に合わせた定着を図るにはどのようなポイントを踏まえれば良いのでしょうか?今回はその重要なポイントを3つに絞って解説します。
クラウドサービスの導入を成功させる3つのコツとは?
1. 導入の目的を明確にする
「クラウドサービスを導入するのはなぜか?」
「どんな課題を解決したいから導入するのか?」
導入を検討する前に一度このような問いを立てて、目的を明確にしましょう。
目的があいまいだと、現場定着せずに結局は使われないシステムになってしまい、一時的な取り組みに終わってしまいます。利用ユーザー含め関係者全員にこの目的が共有されている必要があります。
2. 社内推進体制を構築する
また、スムーズに導入を成功させるためには、社内推進体制を整えることが重要です。システムの導入には様々な問題・調整がつきものであり、それを担当者一人で解決するのは困難です。メンバーを集め、プロジェクトチームをつくることが成功への第一歩です。
プロジェクトチームには、以下4つの立場のメンバーがいると理想的です。
- 決裁者
クラウドサービスの導入目的を周知し、現場理解を得ることに責任を持つ役割の方がいる必要があります。 - 現場責任者
利用者の声を構築担当者へ届けたり、運用の調整をしてクラウドサービスの現場定着を促したり、使いやすさを確認したりすることが求められます。 - プロジェクトリーダー
進捗管理を行うことで遅延を防いだり、問題発生時に対応策を決定したり、構築担当者が構築作業に専念できるように他部署との調整を引き受けたりする役割が求められます。 - 構築担当者
課題解決に向けた設計/構築を行い、利用者を教育して現場定着を促します。
3. スモールスタートを意識する
これは特にノーコード・ノーコードツールの導入に言えることですが、100%完璧なシステムを構築したと思っていても、実際に利用してみると課題や修正点は必ず出てきます。
一気にシステムを全部構築してしまうと、後に修正箇所が見つかった際に修正の難易度や工数が大きく跳ね上がってしまいます。
また、導入期間が長期に渡る計画や対象の業務範囲が大きな計画は、その分不確定要素が大きくなるため、計画にズレが生じると、当初の計画の前提条件も変わるため、再度全体の計画をし直す必要が発生してしまいます。
そのため、大きな計画を綿密に立て、その計画に厳密に従うのではなく、まずは必要最低限の要件を満たしたシステムを作成し、運用しながら現場からのフィードバックなどを通じて、必要に応じて「より使いやすく」カスタマイズしていくといったサイクルが成功へのポイントとなります。構築範囲を小さな単位で抑えることで、修正箇所も最低限に抑えることができるようになります。
クラウドサービス導入のステップ

クラウドサービスの導入は大きく6つのステップに分けられます。スモールスタートを意識するためにも、一旦は最大で3カ月程度のサイクルに区切ることが理想です。
1. 要件の整理(~2週間)
まずは、業務の現状を正確に把握し、ニーズや課題を洗い出すところから始めましょう。
一言でクラウドサービスといっても、その機能や種類は膨大で、多種多様です。課題がわからず目的を持たないと、本当に必要な機能が明確にならず、自社に最適なシステムを選別することは困難です。
また、課題を洗い出す際は、根本原因を追及するようにしましょう。業務課題一つずつに対して解決策を考えるのではなく、複数の業務課題を生み出している根本原因を突き止めた上で解決策を明確にすることで、複数の業務課題を一度で解決できます。また、個別最適の解決策により他の業務課題が引き起こされたり、別の業務を不用意に煩雑にしたりといったことを防ぐことができます。
2. 設計(~2週間)
業務の現状と課題・ニーズと解決策を明確にした上で、システムを設計します。自社にどのような課題があって、これを解決するためには何の機能が必要かを検討し、まずは必要最低限のシステム設計を行いましょう。対応工数がかからず効果が高い領域から進めることができると理想です。
また、設計の際にはシステム化のコンセプトを決めることも重要です。社内のすべての要望を取り入れると開発コストや開発期間が膨れ上がってしまいます。ですから、「このプロジェクトは、誰に、どんな価値を、どのように提供するのか?」というコンセプトを明確にすべきです。例えば、「現場第一」というコンセプトであれば、現場メンバーの入力のしやすさや類似案件の検索機能といった要件に対する設計の優先順位が高くなります。一方「経営視点を持つ」というコンセプトであれば、集計項目の細分化やダッシュボード機能の充実などの優先順位が高くなります。
3. 構築(~1.5ヶ月)
次に設計段階で必要とされた機能を中心にシステムの構築を行います。この期間が最大1.5ヶ月間と他のステップに比べ長くしているのは、構築が特に重要で慎重さが求められるためです。
この段階では、まずは100%を目指さず構築してみることが重要です。構築後は修正点や課題がつきものです。そのため、次のテストの段階でこれらを修正することを前提に、最低限のシステムを構築するようにしましょう。
4. テスト(~2週間)
システムを構築したら、そのシステムで課題が本当に解決できそうか、機能は必要十分かを確認しましょう。また、想定していない操作や手間などが発生していないかの確認も同時に行いましょう。
こうしたテストを十分に行わないと、運用開始後にシステムが止まったり、後の修正が膨大になったり、ユーザーの不満がたまってしまったりと様々な不都合が生じることとなります。
5. 社内教育(~1週間)
現状のシステムで問題がないことが判明したら、システムの社内定着を図るために、構築担当者が中心となり社員の教育を行います。使い方はもちろん、なぜこのシステムで課題が解決できるか、どのように業務を効率化できるのかを資料にまとめたり、実際にシステムを動かしたりして実践的に明示しましょう。
社内教育の時点でシステムに対する現場からの抵抗が上がることもありますが、抵抗を少なくするためには、操作画面のUIの設計等については、設計段階であらかじめ現場責任者の同意を取ることがコツです。
6. 運用開始
以上の約3ヶ月程度のステップを経て、いよいよシステムの運用がスタートします。
クラウドサービスの確かな導入・定着ならお任せください
テレビCM等で目にする通り、クラウドサービスというと便利で導入しやすい面のみが強調されがちですが、上記のポイント・ステップを経ない無計画な導入は、かえって業務の非効率化やコストの増大を引き起こします。
適切な導入ステップをしっかりと踏んで、システムの導入・安定した定着を実現しましょう。
弊社は、課題の抽出・整理から、システムの導入・改善まで一貫してサポートするIT活用支援サービスを、圧倒的なコストパフォーマンスでご提供しています。
クラウドサービスを正しく導入し定着を図り、デジタル化を確実に進めるためにぜひ弊社のサービス導入をご検討ください。
チョイデジは仙台を拠点に全国でDXを進める企業をサポートする会社です。豊富な実務経験を持つメンバーが圧倒的なコストパフォーマンスで皆様の業務効率化をサポートいたします。
「自社の課題が分からない……」
「自社に合ったクラウドサービスがどれか分からない……」
「ビジネス全体の課題を相談できるパートナーがほしい……」
などといったお悩みを持つ方は、遠慮なく弊社にご相談ください。初回相談は無料です。まずは「お問い合わせ」ページに記載のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
